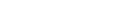トピックス 2019.12.20 若者が危ない?今急増する「デジタル認知症」とは?
デジタル認知症という言葉を聞いたことがありますか?
通常、認知症は高齢者がなりやすい病気というイメージですが、デジタル認知症は年齢を問わずすべての年代の人に症状が発生しうるのです。
「時間があればずっとスマホをいじっているな」「仕事でずっとパソコンの前を離れられない」といったように、デジタル認知症はデジタル機器と密接にかかわっている人のすぐ隣に存在しています。
今回の記事では改めてデジタル機器との付き合い方を考え直すきっかけとして、デジタル認知症とその対策についてご紹介します。
デジタル認知症ってどんなもの?

デジタル認知症とは、デジタル機器(スマホやPCなど)の使いすぎによる情報のインプット過多や機器に対して依存してしまうによって、記憶力・集中力・注意力の低下や言語の障害といった認知症と同じような症状が発生する状態のことです。
認知症と症状が似ているため「デジタル認知症」と名づけられていますが、病気としての認知症とは異なり、したがって病気に分類されるものではありません。
デジタル認知症は一時的な記憶障害にあたるものですが、「若い人ほど影響を受けやすく、悪化すると65歳未満で発症する若年性認知症につながる」と言われており脳に悪影響を与え健康を蝕む症状といえます。
これらの症状が起こることで勉強や仕事へ悪影響を及ぼしたり、良質な睡眠を妨げたり、さらには精神面や身体の健康にまで影響が起こりえると考えると大変恐ろしい症状です。
若者からお年寄りまで。デジタル認知症は現代病?
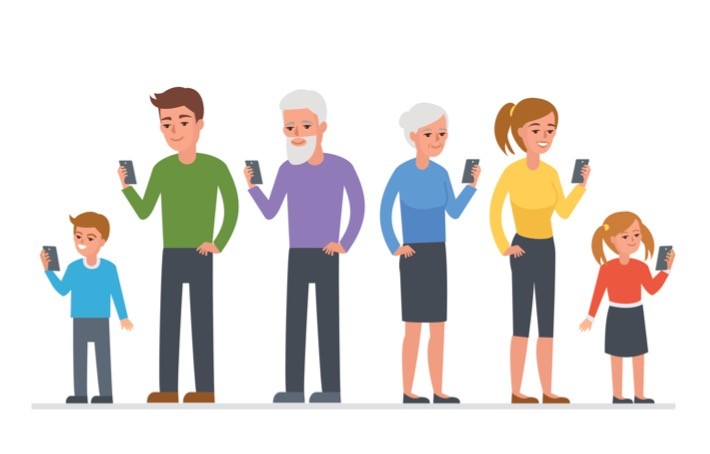
デジタル認知症は高齢者や子どもを含めたすべての年代で症状が発生する可能性があります。
子どもや若年層は、自分でデジタル機器の使い方をコントロールする能力が未熟で没頭してしまいがちです。働き盛りの年齢層では、仕事での情報収集やコミュニケーションツールとしてもデジタル機器が身の回りから離せない人も多くみられます。
さらに近年では、デジタル機器の浸透や進歩によって、高齢者がデジタル機器にはまることが増えているともいわれています。
デジタル認知症の原因は、デジタル機器から膨大な情報をインプットされて脳が情報を処理しきれなくなることから「脳過労」や「オーバーフロー脳」ともいわれています。
これらは加齢が原因で発生するものではないため、デジタル機器を使いすぎてしまうことで年齢には関係なくデジタル認知症となってしまうのです。
過度にデジタル機器を使用する生活習慣が発端となるデジタル認知症は、デジタル機器の普及が進んだからこそ起きえる新たな現代病なのかもしれません。
普段からできるデジタル認知症の対策

デジタル認知症は過度なデジタル機器の使用が原因のため、その予防と対策はデジタル機器と適度な距離を取ることです。
スマホ、PCなどのデジタル機器を使用する上では次のようなルールを設けて適度な利用を心がけましょう。
● デジタル機器を使用後は一定時間の休憩を取る
● 一日の中でデジタル機器を使用しない時間を定める
● 目的がないときはデジタル機器を見ない
● 必要のないアプリやSNSは削除または通知を切っておく
デジタル機器の利用は自己管理で改善できるのがベストですが、うまくいかない場合にはスマホ依存対策アプリといったものもあるため利用を検討してみるのもいいかもしれません。
また、デジタルデトックスといわれる「一定期間スマートフォンやPCなどのデジタル機器を使わない時間を持つことでデジタルデバイスに対し距離を置く取り組み」もあります。
デジタルデトックスのためのサービスなども運営されているため、こういったサービスを利用してデジタル認知症対策に取り込むのもよいでしょう。
終わりに
認知症と呼ばれてはいるものの、一時的な記憶障害であるデジタル認知症はデジタル機器の過度な使用を避けて脳を休めることで脱却が可能です。
スマホやPCに依存せず、ツールとして適度に付き合うことができればデジタル認知症は予防することができます。
ルールを設けてデジタル機器を使用するのは最初は不便さを感じるかもしれませんが、自己を守るため適度なデジタル機器とのつきあいが私たちには求められています。
TEXT:セキュリティ通信 編集部
PHOTO:iStock